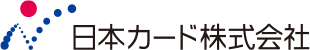飲食店の仕入れのコツ 〜売上データと顧客ニーズの活用方法〜

飲食店経営において、仕入れは店舗の利益を左右する重要な要素です。特に、過剰な仕入れによる食品ロスや、逆に不足してお客様に提供できないリスクは、売上や顧客満足度に大きな影響を与えます。この記事では、デジタルツールを活用して仕入れを効率化し、無駄を減らしながら適切な在庫管理を行うための具体的な方法を紹介します。
売上データの活用による精度の向上
まず、最も重要なのは、券売機やPOSレジから得られる売上データを基に、どの商品がどのくらいのペースでどれだけ売れているのかを把握し、そのデータを元に仕入れを調整することです。例えば、メニューごとの売上個数を1日単位、3日単位ごとに把握し、仕入れ量を調整していきます。これにより過剰な仕入れによるロスの防止や保管スペースの占拠などを減らし、効率的な仕入れを実現できます。
さらに売上データを分析する際には、月ごとの変動や曜日ごとの違いも考慮することが大切で、季節や天候の影響も見逃してはいけません。基本的なところでいうと寒い冬場は温かい鍋料理やスープが売れやすく、逆に夏には冷たいドリンクやデザートの需要が増えることが予想されます。
特に急に暑くなった6月のある日、生ビールが大量に出るようになったり、突然に気温が落ちた11月のある日に鍋物の注文が対応に追われたりといった経験がある方はとても多いと思います。それほど人間の体感温度に対する反応はとても正直です。これは毎年必ず起こることですので、過去のデータとともに確認して行くことは人件費や仕入れ量のコントロールに大いに役立ちます。
食材の消費サイクルの把握
在庫管理は、仕入れを最適化するためのもう一つの重要な要素です。売上データを活用して、仕入れる食材の種類や量を決定するだけでなく、その消費サイクルにも目を向ける必要があります。生鮮食品や加工品にはそれぞれ異なる保存期限があり、この確認を怠ると食品ロスにつながります。
そこで、食材ごとの使用頻度と消費期限を考慮し、仕入れ量を小分けにする方法が効果的です。真空包装機を活用して食品を長期間保存する技術を導入すれば、食材の鮮度を保ちながら無駄を減らすことができます。また、冷凍保存も組み合わせれば、食材の劣化をさらに抑えられます。近年では真空包装機とそのフィルムの需要が増え、ランニングコストもそこまで高価なものではなくなっています。これは小規模な店舗でも、導入の検討をする価値が十分にあります。

顧客ニーズに合わせたメニューの最適化
仕入れの効率化には、メニュー内容の定期的な見直しも重要です。近年では、健康志向の高まりや食の多様化により、ビーガンやグルテンフリーといった特別メニューの需要が増えています。こうした顧客のニーズに対応することは、顧客の選択肢を増やすことになり、食材の種類も増えていくことになります。日頃からしっかりと管理できている店舗は、食材の種類を増やすことに抵抗はない傾向にありますが、この管理ができていない店舗は、種類を増やすことをロスに直結するからと嫌がる傾向にあります。お客様のニーズに合わせて、白米と雑穀米とカリフラワーライスなど選べるようにしたいが、管理が面倒だからと妥協することなく、管理方法を確立していくことも大切です。
また、メニューの提供サイズの多様化やトッピングや付け合わせの柔軟なアレンジを行うことで、仕入れコストを抑えつつお客様に新しい価値を提供することができます。例えば、季節に合わせてトッピングや具材を変更し、メニューに季節感を出すことで、お客様に新鮮な印象を与えることが可能です。そのためにも売上データに基づいて、どの時期にどのメニューが売れているのかを分析し、効率的な仕入れ計画を立てましょう。
デジタルツールによる効率化
現代の飲食店経営では、デジタルツールの導入が不可欠です。特に、券売機やPOSレジといったシステムは、日々の売上データをリアルタイムで収集し、分析することができるため、仕入れ計画の立案に大いに役立ちます。
例えば、毎日の売上を確認しながら、どの時間帯にどのメニューが多く注文されているのかを分析し、そのデータをもとに仕入れ量を調整することが可能です。また、売上のトレンドや季節ごとの変動を予測し、無駄のない発注を行うことで、食品ロスを最小限に抑えることができます。
さらに、デジタルツールを活用した在庫管理システムは、発注漏れや過剰発注を防ぎ、食材の仕入れを効率化するのに非常に有効です。これにより、在庫切れを防ぎつつ、不要な在庫を抱えないように調整することができます。
食材仕入れのコスト削減とロス対策
仕入れコストを抑えることも、飲食店の経営には欠かせません。特に、毎日の仕入れが必要な生鮮食品については、コスト削減と食品ロスの対策がセットで考えられるべきです。まとめ買いやロット仕入れによる単価の削減は、短期的にはコストを抑える方法ですが、余剰在庫が生じやすくなるため、結果的にロスが増えることもあります
そのため、小分けでの仕入れや、納品業者との交渉による適時発注の仕組みづくりが重要です。また、季節によって価格が変動する食材に対しては、あらかじめ複数の仕入れ先を確保しておくことで、安定供給を確保しつつコストを抑えることが可能です。
さらに、仕入れた食材を効率よく使い切るために、定期的にメニューを見直し、セットメニューの組み合わせや量の調整を行うことも効果的です。特に、食べ残しを減らすために、顧客に料理の量やトッピングを選んでもらうシステムを導入することは、仕入れた食材を無駄なく使うための有効な手段です。
食材仕入れパートナー選び
仕入れ先の選定も、飲食店経営の成功に欠かせない要素です。信頼できる仕入れパートナーを選ぶことで、品質の高い食材を安定的に仕入れることができ、食品ロスの削減にもつながります。例えば、地元の農家や漁師から直接仕入れることで、流通コストを抑え、鮮度の高い食材を手に入れることが可能です。
また、規格外の農産物を積極的に活用することも、コスト削減と食品ロス削減の両面で有効です。見た目が規格に合わないだけで品質には問題のない農産物を仕入れることで、通常よりも安価に仕入れができ、なおかつフードロス対策にも貢献できます。
素晴らしい生産者さんとの直接の取引は、一部の料理人だけのものでした。しかし、これまでの時代とは違い現在は、SNSの発達で探し求めている希少で良質の食材やその生産者との接点は、かなり多くなっています。丁寧にコミュニケーションをとることでそのチャンスは十分ありますので、最高のパートナーを探してみてください。

環境に配慮した仕入れの実践
近年、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組む企業が増えていますが、飲食店も例外ではありません。仕入れの段階で環境に配慮した選択をすることで、持続可能な経営を実現することが求められています。
例えば、地産地消を意識した食材の選定や、環境負荷の少ない生産方法を採用する業者からの仕入れを行うことで、飲食店も社会的責任を果たすことができます。また、食品ロス削減のために、無駄のない発注やメニューの見直しを行うことも、持続可能な経営の一環です。
さらに、顧客に対しても環境に優しい取り組みをアピールすることで、エコ意識の高い顧客層からの支持を得ることが可能です。例えば、地元で採れた食材を使ったメニューや、食品ロス削減のための量の選択ができるメニューなど、環境に配慮したサービスを提供することが求められています。
業務用食材の購入方法の変化
飲食店では、業務用の食材を購入する方が割安になるというのが一般的な常識とされています。しかし、ここ数年では、その常識が逆転する現象が起こっています。背景としては、業務用食材の卸業者が人材不足に直面し、さらに車両費やその他の管理費が高騰したことが影響しています。これにより、安価で食材を提供することが難しくなってきています。
その結果、場合によってはネットショッピングで食材を購入した方が安くなることもあります。特に大手のネットショッピングでは、送料が抑えられているため、乾物や調味料類に関しては驚くような価格で仕入れが可能なこともあります。インターネット上の商品は簡単に価格を比較できるため、効率的な仕入れが期待できます。
なお、価格調査を行う際には、情報の量が限られるスマートフォンではなく、PCを使用することをおすすめします。PCでは、複数のウェブサイトを同時に開きながら、詳細な価格比較を行うことができるため、より正確で効率的な調査が可能です。
まとめ
飲食店の仕入れは、単に必要な食材を手配するだけではなく、データを活用して効率的に行うことが重要です。売上データや顧客ニーズを正確に把握し、デジタルツールを活用した在庫管理や仕入れの最適化を行うことで、無駄を削減し、持続可能な経営が可能になります。また、環境に配慮した仕入れ先の選定や、食品ロス削減に向けたメニュー作りも、今後の飲食店経営において重要な要素となるでしょう。