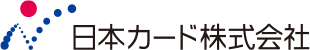「値上げしない勇気」はもう限界?~原材料費高騰に立ち向かうための現場主義的対策とは~

1. 飲食業界を襲う“物価の壁” 〜値上げだけでは済まない時代へ〜
「また仕入れ価格が上がった…」というため息が、厨房の隅々から聞こえてくる。これは今、多くの飲食店経営者が直面している現実です。牛肉、小麦粉、油、調味料など、ありとあらゆる原材料が軒並み値上がりを続けており、仕入れ価格はすでに前年比20~40%以上の上昇という事例も珍しくありません。
今までは「仕入れ努力でなんとか」、「ボリュームはそのままで我慢」といった、“値上げしない努力”で対応してきた店舗も多いでしょう。しかし、今や「値上げしない勇気」は、もはや経営リスクそのものに変わりつつあります。
とはいえ、「ただ値上げをするだけ」では顧客の支持は得られません。原材料費高騰という波にどう立ち向かうか、それには、シンプルな値上げ戦略ではなく、『根本的な経営体質の見直し』が必要です。
この記事では、現場で今すぐ取り組める「具体的かつ現実的な対策」に絞って、メニュー設計、仕入れ、在庫、接客、業務オペレーションまでを含めた全体最適の方法をご紹介します。
2. 価格を上げる“だけ”では足りない 〜経営戦略としてのメニュー見直し〜
最初に着手すべきは、メニュー構成の見直しです。原材料費の高騰により、料理ごとの採算性には大きなバラツキが生じているのが現状です。仕入れコストの上昇をそのまま価格に転嫁していては、客単価が跳ね上がり、来店頻度や顧客満足度に悪影響を及ぼす恐れがあります。
ここで重要になるのが、「利益が出やすいメニューの選択と集中」です。具体的には以下のようなポイントを見直すことが有効です。
• 高騰した原材料を使用する料理を段階的に減らす
• 地域産品や旬の素材を使った低コストメニューを強化
• サイドメニューやトッピングで客単価をコントロール
さらに、単なるコストカットではなく「付加価値の再設計」も重要です。たとえば、主食の量を少し減らし、その代わりに、これまではおまけのような立ち位置だったサラダを彩り豊かな逸品として添えるといった策が必要です。そうすることで、原価率を下げながら顧客の満足度は維持、あるいは向上させることも可能になります。

3. 「仕入れルートの多様化」と「在庫管理の精度」が生き残りの鍵
仕入れ価格を左右するのは、原材料の世界相場だけではありません。意外にも多くの店舗で、ルーティンで発注している“既存の仕入れ先”に過度に依存してしまっていることがあります。
これを見直すだけで、大きなコスト削減につながることもあります。特に、地元の生産者との連携や、複数の業者からの相見積もりによって、「同じ品質の食材をより安く仕入れる」選択肢が見えてくる場合もあります。
また、仕入れだけでなく在庫管理もセットで見直さなければ意味がありません。過剰発注、重複発注、ロスによる廃棄、これらは見えにくい“無駄なコスト”の代表です。
そこで重要になるのが、「データに基づいた発注」です。過去の販売履歴や来店数を元にした適正発注ができれば、必要なものを、必要なときに、必要な分だけ発注できる体制が整います。 また、過去のデータをもとにし、必要な数量を予測し発注するところまでは、多くの経営者が実行できていますが、この予測して発注した数量が実際のところどうだったのかという実績評価まではなかなかできていないようです。このデータを中心としたPDCAサイクルを着実に回していくことが仕入れ、在庫管理の精度を上げるキーポイントとなります。
*PDCAサイクルとは、計画・実行・検証・改善を1連の業務として実行していくこと。

4. ロス削減=利益創出。食材を無駄にしない工夫とは
食材ロスの削減は、コストを抑えるだけでなく、SDGsへの貢献という側面でも近年注目されています。具体的には以下のような対策が挙げられます。
• 先入れ先出しを徹底し、在庫の回転率を上げる
• 使用期限が迫った食材を活用する「日替わりメニュー」の考案
• 小鉢メニューでの食材消費や限定セットメニューの提案を行い、ロスを減らすための仕組みを構築する
特に、スタッフが「何を優先して使うべきか」を明確に理解していないと、食材ロスは見えないところで膨らんでいきます。日々のオペレーションに「ロスを出さない仕組み」を組み込むことが重要です。
5. デジタルツールが 『 もう一人のスタッフ 』 になる時代へ
食材管理に関してもそうですが、これまで人の手で行っていた業務の一部を、デジタルツールで代替できれば、結果として人件費を抑え、間接的に原価率の上昇を吸収することが可能になります。
また、日々の売り上げや来客数等は非常に敏感に把握している場合が多いですが、一つ一つの食材の消費量やメニューの販売数といったところまでは、従業員の記憶では正確ではありません。この部分を人の感覚に頼りすぎる事は、経営としては非常に不安定な材料となります。
ここでご紹介したいのが、日本カードのセルフオーダー端末「smooder」です。
【smooderの導入がもたらす5つの効果】
1. オーダー業務の自動化:スタッフのオーダー対応が不要になり、少人数でも店舗運営が可能に。
2. メニュー改善との連携:メニュー表示を写真付き・言語選択付きで柔軟に編集可能。仕入れ変更によるメニュー改定にも即対応。
3. 注文データの蓄積と分析:人気商品・注文頻度を可視化し、仕入れ量や発注の最適化に活用。
4. 売上向上のアシスト:おすすめメニュー機能やセット提案で、客単価アップも実現可能。
5. キャッシュレス決済の統合:注文から会計まで一貫して完了。会計時のスタッフ負担を大幅に軽減。
そして、大事なポイントとなるのは、smooderは単なる「注文ツール」ではなく、原価管理・在庫計画・販売戦略を支える経営ツールとして機能するという点です。

6. コスト構造の見直し
〜人件費25%、デジタル投資8~10%という新常識〜
従来、「売上に対して人件費30%」が適正ラインとされてきましたが、昨今の採用難や賃金上昇を考慮すると、30%を超え35~40%に達している店舗も少なくありません。
この流れを是正するためには、「人だけに頼らない店舗づくり」が前提になります。smooderのようなセルフオーダー端末、デジタルメニュー管理、AIによる予測発注といったツールに売上の8~10%を投資するという戦略的判断が、今後の飲食店の標準モデルとなっていくでしょう。
むしろ、アナログに頼り続けて人件費比率が40%を超えてしまえば、その店舗の未来は極めて不安定になります。 「人にかけていたコストを、デジタルツールにできる限り置き換えていく。」という意識が、今こそ必要です。
7. 値上げの伝え方も、経営者の腕の見せ所
最後に一つ、忘れてはならないのが「値上げをどう伝えるか」です。原材料費の高騰により、一定の値上げは避けられないとしても、これを唐突に実施しては顧客の反発を招きます。
そこで重要なのは、「値上げ=品質維持のため」「値上げ=スタッフの待遇改善のため」といったストーリー性を持たせ、顧客の理解を得る努力を怠らないことです。
• 「材料費が値上がりしたが、代替となるような食材はない。」と伝える。
• 「より良いものを提供するために、店舗環境と従業員のケアのため」と伝える。
こうした細かな配慮が、値上げに対する心理的ハードルを下げ、顧客離れを防ぐ鍵となります。
また、経営者は特にお客様の気持ちになりすぎて、必要以上に値上げに対して恐縮する態度を見せることがあります。今のご時世は、物価が軒並み上昇している状況で、社会的にもやむを得ないことを認識してくれていると考え、はっきりと堂々とした態度で値上げを実施することも大事なことです。

8. 原材料費高騰の時代を「勝ち抜く」店になる
原材料費の高騰は、一過性の問題ではなく、今後も継続的に影響を与える可能性が高い構造的な課題です。だからこそ、根本的な体質改善が求められます。
• メニューの戦略的再設計
• 仕入れ先と在庫の見直し
• 食材ロスの徹底削減
• デジタルツールによる効率化
• 顧客との誠実なコミュニケーション
そしてその中心に、「smooder」のようなデジタルツールを常設しておくことが、未来の飲食店経営を支える勝ち筋となるでしょう。単に値上げするのではなく、これまでの収益モデルを再構築するぐらいのイメージで、変革の一歩を踏み出していきましょう。