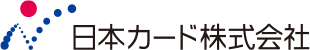飲食店の人手不足を逆手に取る!採用難を突破するシフト戦略とIT活用

近年、飲食業界では深刻な人手不足が続いています。少子高齢化による労働人口の減少、若年層の飲食業界離れ、アルバイト応募の減少といった複数の要因が絡み合い、採用の難易度は年々高まっています。さらに、コロナ禍を経て、多くの飲食店が営業再開に月日が経ちましたが、以前にもましてスタッフを確保できないという課題に直面しています。
このような状況において、「人手不足=経営努力でカバーして当然」といった従来の考え方では、スタッフの負担が増大し、結果的に離職率の上昇を招くという悪循環に陥りがちです。しかし、シフト戦略の見直しやITツールの活用により、限られた労働力でも効率的な店舗運営を実現することが可能です。本記事では、飲食店が抱える採用難の背景を分析し、持続可能な経営を目指すための具体的なシフト戦略とIT活用の方法について解説します。

1. なぜ飲食店は人手不足に陥りやすいのか?
飲食業界は、他の業種に比べて特に人手不足が顕著です。その要因として、不規則な勤務時間や低賃金、過酷な労働環境が挙げられます。長時間労働が当たり前とされる業界のイメージは、求職者に敬遠されやすく、結果として採用のハードルが上がっています。
また、業務の効率化が十分に進んでいない店舗では、限られた人数で多くの業務をこなさなければならず、スタッフの負担が増加します。その結果、離職率が高くなり、さらに人手不足が悪化するという負のスパイラルが発生します。このような状況を放置すれば、顧客満足度の低下、クレームの増加、売上の減少といった深刻な影響を招く恐れがあります。特にクレームの増加は、働くスタッフへの精神的な大きな負担になるため、これが離職の原因となる場合も少なくありません。
2. 採用難を突破するためのシフト戦略
1)柔軟なシフト組みとスタッフのモチベーション管理
従来の固定的なシフトでは、スタッフの希望に沿えないことが多く、結果的に離職の要因となります。そこで、希望シフト制(自己申告制)を大前提とし、可能な限りスタッフの希望を反映させることが重要です。特に今の若い世代は、給料等の金銭的な欲求よりも、自分の時間を十分に確保できることが職場選びの際の大きなポイントになってきています。正社員の労働条件でさえも、週休3日制などの雇用条件を選択肢として用意することも視野に入れるべきでしょう。また従来では残業=稼げるというイメージがありましたが、これを歓迎するスタッフは、少数派になってきていると考えるべきです。労働力を十分に確保し、勤務を延長することはなく、早く帰れる日が多い状態をスタンダードにするべきでしょう。また、シフト管理アプリを活用し、勤務希望を可視化することで、スタッフ同士の協力体制を強化し、スムーズなシフト調整を可能にすることも必要です。
2)繁閑に合わせた配置最適化
ランチやディナーのピークタイムなど、店舗の混雑が予想される時間帯に重点的に人員を配置することで、少人数でも効率的な運営を実現することが基本的業務になりますが、そのためには過去の売上データを分析し傾向を割り出すことが第一歩となります。シフトを組むことで、人件費の最適化も図ることができます。特にアルバイトやパート勤務の方が多い店舗においては、この売り上げ予測とスタッフ配置の適正化は利益の確保に直結する重要なコントロールポイントとなります。また人員的には適正人数がシフトに入っていたとしても、その時間帯に応じて店長や責任者等の指示により細かい配置や必要な動きを取ることも、効率的な運営を目指す上では非常に重要になってきます。同じ人数がいても、店長や責任者次第で売り上げが10%ほど変わることも珍しくありません。

3)給与体系・福利厚生の見直し
スタッフの定着率を高めるためには、評価基準や福利厚生の見直しも欠かせません。特に飲食業界では、個々の能力を評価する基準をさだめるのが非常に難しいことが多いようです。 飲食店からの離職の最大の理由の一つに、『頑張っているのに評価されないから』という点が挙げられます。スタッフの能力を評価する階級制やインセンティブ制度を導入し、成果に応じた報酬を設定することで、スタッフのモチベーション向上につながるよう細部まで整備を進めるべきです。また、食事補助や休憩環境の整備なども長期的な雇用維持の鍵となります。
3. IT活用がもたらす飲食店の変革
現在の飲食業界では、人件費を制御するために重要な経費として、デジタルツールに支払う経費が挙げられます。十分な人員を確保できない分、いかに効率的にデジタルツールに置き換え、それを活用するかが人件費や食材費をコントロールするのと同じように重要な経営ポイントになってきます。特に以下のようなIT・デジタルツールに着目するべきでしょう。
1)セルフオーダー端末の導入メリット
近年、多くの飲食店で導入が進んでいるセルフオーダー端末は、人手不足対策として非常に有効なツールです。オーダー業務を自動化することで、スタッフは接客サービスや調理の質向上に専念できるようになります。また、オーダーミスが削減されることで、スタッフの教育コストやクレーム対応の負担も軽減されます。またお客様のスマホ自体をセルフオーダーの端末として利用することも可能です。
2)AIやクラウドを活用したシフト管理
AIを活用したシフト管理システムを導入することで、スタッフの過去勤務実績や売上予測データを分析し、最適なシフトを自動作成できます。突発的な欠員にも迅速に対応できるため、店舗運営の安定化につながります。また店長等管理者に負担をかける勤務希望時間の収集やシフト決定後の個々への連絡などをシステム上で完結することができる便利なツールも存在します。これらをうまく活用するべきでしょう。
3)キャッシュレス決済・在庫管理システムとの統合
セルフオーダー端末とキャッシュレス決済、在庫管理システムを連携させることで、注文から決済、在庫管理までの業務を一元化できます。これにより、オペレーションが効率化され、スタッフの負担軽減と顧客満足度の向上を同時に実現できます。特に会計関連のシステムはお客様とスタッフ、双方の待機時間を極限まで減らすことができます。人材不足の今1番最初に導入を検討するべきでしょう。
4)新人教育やマニュアル・レシピ・作業手順等のデジタル化
現在、マニュアルや作業の手順書等をアーカイブやデータベースに保存し管理することで、効率的なスタッフの教育をすることが可能です。このように管理された資料や動画は店舗外でも好きな時に、スマホやiPadなどの端末で確認できる点が便利です。これを実現するために日ごろから店舗作業の一つ一つを整理して保存しておくことが重要です。導入するためには膨大な量の資料を整理することになり、大きな負担となりますが、一度ここを整備すれば非常に効率的な教育につなげることができるはずです。場合によっては、何日か休業してでも整備し、その後の経費削減につなげるべきでしょう。

4. 日本カードの「smooder」導入で期待できる成果
1)省人化&スタッフの負担軽減
日本カードのセルフオーダー端末「smooder」は、直感的に操作しやすいUIを採用しており、高齢スタッフや外国人スタッフでも簡単に利用できます。これにより、従業員のオーダー対応の負担を軽減し、接客業務の効率化が図れます。
2)売上アップと顧客満足度の向上
「smooder」は、オーダーミスの削減に加え、追加注文やおすすめメニュー表示機能を搭載しており、客単価の向上が期待できます。また、混雑時の待ち時間を短縮することで、顧客満足度の向上にも貢献します。さらに日々の来客情報をデータとして吸い上げ分析することで、より実情に合ったシフト作成をすることが可能になります。
3)導入・運用コストを抑えた投資回収モデル
「smooder」は初期費用の負担を軽減する導入プランを用意しており、運用もシンプルなため、スムーズな導入が可能です。導入後の運用支援も充実しているため、それぞれの店舗に適した形で活用できます。
5. 成功のための導入プロセス
1)店舗の課題洗い出しと目標設定
まず、売り上げ予測やシフトの作成内容、業務フローのどこに問題があるのかを明確にし、ITツールを活用して解決すべきポイントを整理します。
2)スタッフへの丁寧な説明と研修
新しいツールの導入には、スタッフの理解と協力が不可欠です。導入前に研修を実施し、使い方やメリットをしっかりと説明することで、スムーズな運用が可能になります。

3)導入後の運用モニタリングと改善
導入後は、利用状況やスタッフ・顧客のフィードバックを定期的に収集し、UIの改善や設定変更を行いながら、最適な運用を目指します。
6. まとめ
人手不足が深刻化する中、飲食店経営者は柔軟なシフト戦略とITツールの活用を通じて、持続可能な店舗運営を実現する必要があります。日本カードの「smooder」は、限られた人手でも効率的なオペレーションを可能にし、売上アップと顧客満足度向上を同時に叶える最適なソリューションです。人手不足の課題を逆手に取り、新しい経営の形を構築していきましょう。