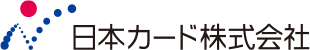飲食店の可能性を広げる、外国人雇用という選択肢~デメリットを恐れず、戦略的に活用するための実践ガイド~

1. 人手不足の解決策としての「外国人雇用」
「もう誰も応募してこない」「求人広告に月10万円かけても結果ゼロ」——これは、今や飲食業界では珍しくない声です。長時間労働、厳しい現場、そして相対的に低い賃金という飲食業の構造的な課題は、国内の若年労働者離れを招き、結果として深刻な人材不足を招いています。
この状況下で注目されているのが、外国人材の雇用です。2023年末時点で、日本国内の在留外国人数は過去最高を更新し、特定技能や留学ビザを利用した労働人口も増加しています。飲食業界においても、外国人スタッフの採用は「特例」ではなく、すでに多くの店舗が実践している「現実的な選択肢」となりつつあります。
日本の労働人口の減少と高齢化を考えれば、外国人労働者を雇用する事は、今後さらに常態化する事は間違いありません。
とはいえ、文化や言語、制度理解の壁など、課題も多く、二の足を踏む経営者が多いのも事実です。このコラムでは、外国人スタッフの雇用におけるメリットとリスクを多角的に検討し、現場が抱えるリアルなシーンに即した実践的な解決策を提示します。
2. 外国人雇用のメリットとは?
外国人スタッフを受け入れる最大の魅力は、やはり長時間労働や過酷な労働環境に耐久性がある人が多いという点です。また、特に母国で飲食業に従事していた経験者は、包丁の扱いからオーダー処理まで、短期間で習熟して戦力化しやすい傾向があります。
また、観光需要が高まる中で、英語や中国語、韓国語などを話せるスタッフが在籍していることは、外国人顧客への対応力という点で店舗の競争力を大きく引き上げます。実際、京都や浅草の繁華街では、外国人スタッフが「観光地ならではの接客体験」を生む重要な存在となっています。
さらに、文化的な背景の違いが店舗運営に新しい風を吹き込むことも少なくありません。たとえば、カフェにおいて、ベトナム人スタッフから「母国の定番料理をアレンジしたベトナム風サンドイッチ」の提案があり、それがヒットメニューにつながったといった事例もあり、異文化が交わることで、飲食店の創造性や柔軟性が広がることは間違いありません。

加えて、技能実習や特定技能といった制度を正しく活用すれば、数年単位での雇用が可能になり、「辞めない人材」として計画的に育成していける点も見逃せません。
3. 見落としがちなデメリットとその対応策
しかし、外国人雇用には当然「手間」が伴います。単なる人手不足の穴埋めとして考えると、受け入れ後に「思っていたのと違う」というギャップに苦しむことになります。
たとえば、言語の壁は最初の大きなハードルです。指示が通じない、注文が聞き取れない、お客様との会話がスムーズにできない——これらはすべて業務品質に直結する課題です。ただし、「やさしい日本語」を用いた指導や、翻訳アプリ、音声翻訳機などのツールを併用すれば、現場レベルでも十分な対応が可能です。
文化的ギャップにも注意が必要です。たとえば、時間感覚や報告の習慣が日本と異なることで、「勝手に判断された」「指示を無視された」と感じるケースもあります。しかしこれは教育の問題というより、「どう伝えれば理解されやすいか」の工夫が足りないだけのことが多いのです。定期面談の実施や、業務ルールを図解付きで明示することが大きな助けになります。
また、在留資格に関する法制度の理解不足もリスクです。誤って不適切な就労条件で雇用してしまえば、店側にも法的責任が及びます。ここは専門家(行政書士や人材紹介会社)の支援を受けて制度設計から入るのが現実的です。
そして、従業員の就労準備に対してもケアが必要です。最初の2〜3ヶ月でしっかりとサポートを行い、業務習熟と生活安定の両面を支える体制を整える必要があります。たとえば、スタッフ用の住居探しや銀行口座の開設支援、生活ルールの説明など、就業間際の支援がその後の定着率に大きく影響します。

4. 外国人材活用を成功させるための具体策
外国人雇用を“人材活用”として根付かせるには、準備と工夫が不可欠です。次のような具体的なアプローチが効果的です。
•採用段階での要件設定
「日本語検定N3以上」や「週末勤務可能」など、あらかじめ期待する条件を提示し、面接では翻訳ツールも駆使して意志確認を徹底します。とりあえず採用してから話し合いながらといった曖昧な条件は大きなトラブルになることが多いようです。
•業務マニュアルの可視化
写真入りの業務手順書や動画マニュアルを整備し、「見て理解できる」仕組みに。接客フレーズ集を用意するだけでも大きな安心材料になります。
•生活支援とメンタルケア
仕事の悩みだけでなく、日常生活での不安(家賃・健康・人間関係)を吐き出せる相談体制を整えることが、結果的に職場定着率を大きく押し上げます。この点に関しては、外国人であろうが、日本人であろうが、同じことでしょう。
•多言語コミュニケーション環境
SNSでのグループトークに翻訳ボットを入れる、ポスターや業務連絡を多言語対応にするなど、日常の「ちょっとした壁」を減らす工夫が有効です。
•周囲の理解醸成
採用する外国人スタッフに対する教育に目を向けがちですが、他の既存スタッフへのオリエンテーションや「文化の違いを尊重するための研修」も併せて実施することで、現場での摩擦を防ぎ、チーム全体の協力体制を築くことができます。

5. 日本カードの「smooder(スムーダー)」で外国人スタッフの即戦力化を促進
こうした環境整備に加え、業務そのものを簡素化するツールの導入も非常に有効です。その代表例が、日本カード株式会社の提供するセルフオーダー端末「smooder(スムーダー)」です。
外国人スタッフにとって、もっとも大きな負担となる「注文のやりとり」や「会計処理」を、smooderが代行してくれることで、言語の壁がほぼ解消されます。特にUI(画面操作)がシンプルで直感的なため、日本語が得意でないスタッフでも短期間で習熟できます。
また、オーダーミスや釣り銭ミスのリスクも減るため、現場の心理的負担が大幅に軽減され、「本来集中すべき接客や調理業務」に集中できるようになります。結果として、外国人スタッフの即戦力化が進み、「雇ったけど戦力にならない」という事態を防ぐことができます。
さらに、導入費用や保守体制も中小飲食店向けに最適化されており、初期コストを抑えたスモールスタートも可能。人手不足を前提とした運営の「仕組みづくり」に欠かせない一手として、多くの店舗で導入が進んでいます。

6. まとめ
外国人雇用を検討する際、単に「人手を確保するため」という理由だけで導入すると、かえってミスマッチや早期離職を招いてしまいます。しかし、制度理解・現場設計・教育の仕組み・ツール導入をセットで捉えれば、飲食店の新しい可能性を切り開く大きな力となります。
異なる文化や言語を持つ人材とともに働くことは、単なる「人員補充」ではなく、「店舗文化の刷新」や「顧客満足度の向上」につながる、未来志向の戦略的経営です。
smooderのようなツールを導入し、受け入れの土台をしっかり整えることで、外国人スタッフも、既存スタッフも、顧客もすべてが安心して関われる店舗運営が実現します。
「人手が足りない」と悩むだけでなく、「この機会に体制を見直そう」と前向きに捉えることで、これまでにない店舗の成長がきっと生まれます。まずは、業務負担を減らすツールの活用から始めてみませんか? そしてその先に、文化を越えて共に働く喜びと、新しい飲食店の未来が見えてくるはずです。